どうも、みずきちです。
生きているとミスをします。
学校でも仕事でも、遊んでいるときでさえミスは起こります。
僕も数えきれないくらいたくさんのミスをしてきました。
振り返ってみると確認不足が原因だったり、よく考えればわかることを深く考えなかった結果ミスにつながったなんてことが多いんですよね。
ミスをしてからだと
「こんな簡単なことをどうして…」
と思うのですが、当時はミスをするなんて気づくことはできませんでした。
あなたにもきっとそんな経験があると思います。
ミスなんてそんなもんだから切り替えよう。
と考えることもできますが、減らせるものは減らしたいですよね。
「慣れ」が招くミスはなぜ起こるのか、どうすれば減らせるのかを解説します。
ケアレスミスの原因

ケアレスミスとは不注意による誤り、軽率な間違いのことです。
普段は注意深く確認をしているのにたまたまそれを怠ったとか、習慣になっているからと深く考えずにとった行動が間違っていたとかで発生するものをいいます。
なぜ確認を怠ってしまうのでしょうか?どうして深く考えずに無意識下で行動をしてしまうときがあるのでしょうか?それは人間の思考の構造によるものと言えるかもしれません。
システム1・システム2
心理学者であり、行動経済学の権威のダニエル・カーネマンが提唱したシステム1とシステム2という思考方法があります。
システム1は自動的に高速で行われる思考で、努力を必要とせず自らでコントロールをすることができないという特徴を持っています。例えば1+1=?とか、日本の首都は?と聞かれると瞬時に答えが頭に浮かんできますよね。答えを導き出すのに何の努力も必要とせず、考えたという感覚すらなかったのではないでしょうか。これがシステム1です。
一方システム2は努力が必要で、簡単に答えが出せず深く考えるときなどに使います。また、システム1が出した直感が正しいかチェックする役割も持っているのですが、それをよくサボるという特徴があります。
はじめての作業は自動的にはできません。メモやマニュアルを見ながらだったり、合っているか不安の中でおこなわれることが多いかと思います。この時はシステム2が働いています。
ところがこの作業がルーチンとして毎日の業務に組み込まれているとどうでしょう?
日々を過ごす中で、慣れることで非常に簡単な作業に移り変わっていきます。いつしかシステム2ではなくシステム1を使って自動化されます。
基本的にはシステム1は正しいことをします。そのため自動化されてもほとんどの場合は特に問題ありません。ところがシステム2はよくサボるのです。たまたま入力ミスをしたとか、書き間違いや計算間違いをしているのに見落としてしまうことがあります。
その結果、ケアレスミスが生まれてしまうのです。
流暢性に気を付けよう
流暢性とはものごとに「ひっかかり」がないことです。
文章を読んでいるときに似たような文章だとすらすらと読み進めることができますよね。
改めて説明をしますがシステム1は基本的に正しいことをします。そのため自動化されてもほとんどの場合は特に問題ありません。
すぐ上に書いているので当たり前なのですが、見たことのある文章ですよね。
特にひっかかりもなく流し見程度でも意味が伝わります。
ただ、これが似たような文章だけれど意味が違うとか、指示が違う、問題文が少し違うといったことになるとシステム1がエラーを起こしてシステム2がスルーをしてしまうかもしれません。
システム1は基本的には正しいことをするので、自動化されてもほとんどの場合は問題ありません。
ところがシステム2はよくサボるのです。
どうですか?
流暢性をなくすために装飾をしました。一気に内容が入りやすくなったのではないでしょうか。
なんとなく知っている、見たこと聞いたことがあると、流暢性が出てくるので自動的に処理がされやすくなります。そんなときはケアレスミスが非常に発生しやすくなっています。
「いま流暢性が上がっているな」というサインを見落とさないようにできれば理想ですが中々難しいですよね。流暢性が高い=ケアレスミスが発生しやすい状態になっている。ということを理解しているだけでもかなり差が出ますので意識してみてください。
疲れているときはケアレスミスが起きやすい?

ケアレスミスを起こしやすい、つまりシステム1に頼りがちなときはどのようなシーンなのかを明らかにした研究があります。それによると以下の6つときにシステム1による自動的な意思決定を下すことが多いようです。
1.疲れているとき
2.選択肢、情報量が多いとき
3.時間がないとき
4.モチベーションが低いとき
5.情報が簡単で見慣れているとき
6.気力、意思の力がないとき
5は上述の流暢性です。
2に関しては、選択オーバーロード、情報オーバーロードと呼ばれているものです。
1.3.4.6を要約すると思考と意思決定に時間を割く余裕がなかったときです。
疲れているときは深い思考をする能力が残っていませんし、時間がないときは意思決定に時間を割く余裕がありません。夏休み終盤の宿題を適当に済ましてしまうときとか、提出ギリギリの課題が雑になってしまうといった経験はあなたにもありますよね。
モチベーションや気力、意思の力がないのはある種やる気がない状態、意思決定に対してどうでもいいと思っているので適当にこなした結果、当然ケアレスミスが増えます。
ケアレスミスをどうやって減らすか
上記をまとめるとケアレスミスには発生しやすいタイミングがあります。
タイミングを理解したうえで対策をとることができれば、ゼロとは言わないまでも数をかなり減らすことが可能です。
真剣に取り組む
当たり前の話ですが、一番重要です。
真剣に取り組んでいたのにミスをしたときの対策を求められているかもしれません。
でも改めて思い返してください。
過去のケアレスミスの際、なんとなくでやっていたり見直しを怠りませんでしたか?
ケアレスミスとは簡単なミスなのです。
テストが終わってからの見直しや、仕事上の業務をこれでもかと後追いするといったことを徹底するのが一番手っ取り早い方法です。
時間に余裕を持つ
意思決定に時間をかけましょう。
いくら真剣に取り組んでいても時間に追われているとケアレスミスから逃れることができません。
朝の忘れ物をなくすには1時間早起きする、ギリギリになるまで業務を後回しにせず早めに手を付けてしまうなど、時間の対策をきっちりとしましょう。
行動経済学的な対策
一貫性の法則を利用する
一貫性の法則とは、自分の行動や信念に一貫性を持たせようとする心理効果です。
禁煙やダイエットを、周囲に宣言したり紙に書いたほうがいいと言われる理由の一つは一貫性の法則が働くからです。示した態度に一貫性を持たせようと思うので、継続しやすくなります。
例えば宿題をいつやるとか、何時に起きるとかを宣言しましょう。それだけで宣言しないときと比べても非常に簡単に行動に移せるようになりますよ。
できるだけ具体的に計画を立てる
計画に無理があると、計画通りに進めていても時間の余裕がないなんてことになるかもしれません。
そもそも私たち人間は計画を立てるときの時間や予算を見誤るという認知バイアスを持っています。
「計画の誤謬」というのですが、イレギュラーを組み込んでいなかったり、そもそも理想的に物事が進むことを前提に計画を立ててしまうことが原因です。
テスト勉強や提出書類、長期プロジェクトの計画を立てる際は、風邪なんかの体調不調や急な予定などを想定するのが理想です。ただ、すべてを見通すことなどできません。例えば想定の1.5倍は見ておくなど、当初の想定通りにはいかないことを前提に予定を立てましょう。
また、各タスクを細分化して管理することも有用です。
意外とできないことを理解する
流暢性のやっかいなところとして、見慣れたものは簡単そうに見えるという点があります。
上司や先輩に見せてもらった作業を自分でやろうとするとできなかったという経験はないですか?
スキルが高い人は簡単そうに作業をこなします。それを見ていると簡単なんだな、と思ってしまいがちですよね。でも決して作業自体が簡単なわけではないことがほとんどです。
できると思って軽い気持ちで取り組むと、ミスの元です。
「簡単そうに見える=流暢なもの」は必ずしも本当に簡単ではありません。
まとめ
ケアレスミスは誰もが経験します。
僕も学生時代、社会人時代に山のようにケアレスミスをしてきました。
頭がいいとかどうとか関係なく、合理的ではない意思決定には傾向があります。
どうして意思決定にエラーが起きるのかを理解しているかどうかで、取る行動が変わります。
・システム1が先に自動化処理して、後からシステム2がエラーを調べるが頻繁にサボってしまう
・慣れによる流暢性がある文章や言葉は意思決定が自動化処理されやすい
・意思決定に時間を割く余裕がないときはケアレスミスが発生しやすい
この3つを理解するだけでも、ケアレスミスが発生しやすい場面がわかります。
発生しやすいときには対策を取りましょう。
・真剣に取り組む
・時間に余裕を持つ
そのために
・一貫性の法則を利用する
・計画を立てる際はかなり多めに見積もっておく
・流暢=簡単ではないことを理解する
以上のことをおすすめします。
ケアレスミスは認知バイアスが多く関わっています。
発生しやすいタイミングがあります。
適切な認識と対策でできる限りケアレスミスの数を減らしていきましょう。
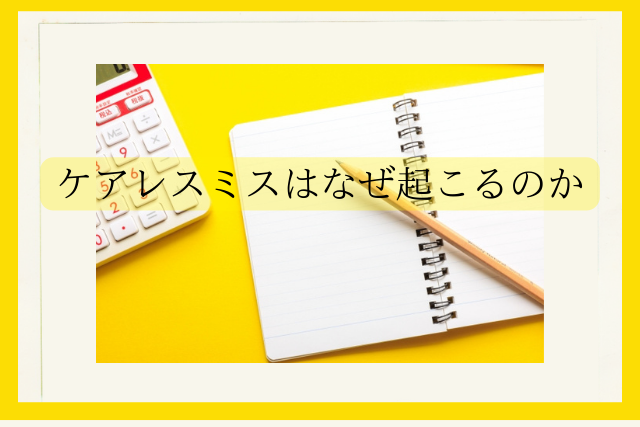
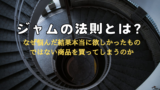




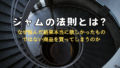

コメント