どうも、みずきちです。
数年前から脚光を浴びて名前だけは知っているなんて方も増えてきた行動経済学。
本屋に行くと行動経済学に関する書籍が山のように置いています。
行動経済学を学べば投資に勝てるだとか、ほとんどの人間をいとも簡単に操ることができるようになるだとか、まるで魔法のように書かれたタイトルを目にしたことがあるかもしれません。
でも、行動経済学ってそもそも何?
経済学だったら難しそうだし、向いてないかな…。
調べてみたけれどよくわからない…。
うさんくさいし嘘っぽい。
一度調べたときにそんな風に思ったかもしれません。
しかしビジネスでもプライベートでも役立つ知識がたくさんあります。
ある程度知っていて、損をすることは決してありません。
今回はそんな注目の行動経済学とは何なのかをできる限り簡単に解説します。
行動経済学とは?の前に「ホモ・エコノミクス」とは?

伝統的な経済学の大前提として、ホモ・エコノミクス(経済人)という概念があります。
ホモ・エコノミクスは極めて合理的で、個人の利益が常に最大化されるよう判断をして意思決定を下す人間です。
少し難しいので例を出しましょう。
洗濯用洗剤を買うときに支払う費用と効果(汚れの落ち具合、香りや洗濯物の仕上がり)を販売されているすべての洗剤を比較検討をして、もっとも費用対効果が高いものを選びます。
一度ダイエットを決意したらつい食べ過ぎてしまったなんてことは絶対に発生しません。
寝坊もしないし就職や進学で失敗しません。無駄遣いも利益が最大化されないのでするはずがありません。
つまりホモ・エコノミクスはこの世のすべての商品を把握するほどの頭脳を持っていて、精神力が強いどころかそもそも誘惑されない特殊体質の持ち主である完璧人間、もはやロボットなのです。
そんな人いますか?
あなたはどうですか?洗剤を購入するときはそんなに知識がなくてなんとなく知っているものを買うし、ダイエットをしているときは甘いものや揚げ物に誘惑されて時には負けてしまいますよね。
ついコンビニで無駄遣いをしてしまうこともあるでしょう。
ホモ・エコノミクスなど存在していないのです。
行動経済学とは?
現実の経済を動かしているのはホモ・エコノミクスではなくヒューマンです。
伝統的な経済学からみて合理的ではない意思決定をしょっちゅうしてしまう僕やあなたです。
人間の心理面を考慮しないと本当の経済の動きはわからない、ということで20世紀半ばごろから急速な発展を遂げていきました。
簡単に言ってしまえば
経済学+心理学=行動経済学と言えます。
伝統的な経済学では考慮されていなかった合理的ではない部分が重視されています。
機嫌が悪いときは乱暴な対応をしてしまったり、疲れているときに無駄遣いをしてしまったり。
いましなければならないことを先送りにしてしまったり。
合理的ではないことばかりしてしまいますよね。
行動経済学とは人間の行動を解き明かすことが目的の比較的新しい学問です。
行動経済学の基本的な考え方

朝食になにを食べるかを決めたり、その日着る服を選んだりと、なにかを選んで判断することを意思決定と言います。人生は意思決定の連続です。
ケンブリッジ大学のバーバラ教授によると、人は1日に3万5,000件の意思決定をしているそうです。
3万5,000回も真剣に検討をしたうえで意思決定をしていると時間がいくらあっても足りませんし、脳がパンクしてしまいますよね。そうならないためにほとんどの意思決定を自動化しています。
経験からくる予測や、より簡単な問題に置き換えて考えることで簡略化する思考プロセスのことをヒューリスティックといいます。
具体例をあげましょう。
「喉が渇いているからなにか飲み物を買いたい」と思っているとき、本来はどれくらいの喉を潤せるのかはもちろん、手元にあるお金や今後発生するであろう出費や味、サイズに味など、検討しなければならないことはたくさんあります。
でも普段コンビニで飲み物を買うときはそこまで考えて買いますか?
いつも買っているから水にするとか、流行っているから新作のジュースにするとか、好きなタレントがCMに出演しているコーヒーにするとか、まったく違う判断基準に置き換えて購入していますよね。なんならそんな意識すらしていないかもしれません。
ほとんどの場合それで問題は起こりません。ただし、本当は論理的に考えるべきところを省いているのでするべき行動との間で歪みが生じることがあります。
この歪みのことをバイアスといいます。
より詳細に説明をするとシステム1とシステム2なんて言葉もあるのですが今回は割愛します。
やってはいけないと禁止されたことをやりたくなってしまったり、課題をつい後回ししてしまったりと、合理的ではない判断をしてしまいやすいときはパターンがあります。そのパターンを解明して対策をとることでより良い人生にしていきましょう。
代表的な心理効果

ビジネスや日常生活に活かせる心理効果を抜粋して紹介します。
ここで紹介するものを覚えていただいて意識するだけでもあなたに大きなメリットがあるのでぜひ覚えてくださいね。
利用可能性ヒューリスティック
自分が入手しやすい情報を大きく評価して意思決定を下すヒューリスティックです。
口コミや友人の評価、あなた自身の印象に残っている出来事のような思い出しやすい情報は過大評価されやすい傾向にあります。
ほとんどの人が低評価なのに1人の友人が気に入っていたからと、品質の低い商品を購入してしまったり残念なサービスを利用してしまうなんてことがないように注意しましょう。
災害の対策をとるのは素晴らしいことですが、災害や飛行機事故の直後に、発生するリスクを過大評価してしまうのも利用可能性ヒューリスティックの仕業です。
代表性ヒューリスティック
いわゆるステレオタイプのイメージで判断してしまいやすいことを代表性ヒューリスティックと言います。関西人だから陽気でおしゃべりな人だろう。とか、理系だから理屈っぽくて気難しいとか文系だからお酒を飲んで騒いでいるんだろうとか。そんな根拠は全くないのになんとなく「それっぽい」代表的なイメージで判断して意思決定をすると大きなミスを起こしかねません。
フレーミング効果
同じ内容でもどこを切り取るか、どこに焦点を当てて説明をするかで異なる意思決定を下してしまう心理効果です。「この手術は90%の確率で成功します」と言われるのか、「この手術は10%の確率で失敗します」と説明されるのかで印象は全く異なりますよね。
たとえば面接や営業時などで意識をしてみてください。言っていることは同じなのにアピールになるのかデメリットを説明してしまう結果になるのか違いが出ます。
デフォルト効果
「ナッジ」と呼ばれる行動経済学や心理学のテクニックを使った”促し”で使われるのですが、ほとんどの人は初期設定に従います。有名なのは臓器提供の意思表示ではないでしょうか。日本や韓国、ドイツなどの国は、臓器提供の意思があると表明することで提供ができる「オプトイン方式」です。一方イギリスやスペインは臓器提供をしないことを意思表示しない限りは臓器を提供する意思があるとみなす「オプトアウト方式」をとっており、デフォルトが臓器提供ということになります。デフォルトがどちらなのかによって実際の提供数、提供の意思表示の割合に著しい差が出ます。
日本臓器移植ネットワークより引用 https://www.jotnw.or.jp/explanation/07/06
日常生活では、何らかのサイトに登録をした際にメルマガを受信するかどうかの登録で、受信をするに最初からチェックが入っているサイトが多くなりました。これはまさにデフォルト効果を狙ってのことです。中には悪質なものもありますので、デフォルト効果の存在を意識しましょう。
確証バイアス
あなた自身の信念や考え、立てた仮説に対して肯定的な意見ばかりを集めてしまったことはないですか?もしあるとすればそのときはまんまと確証バイアスの餌食になっていたと言えます。
自分の意見を肯定してくれる評価や裏付ける根拠にばかり目がいき、反証をシャットアウトしてしまう心理効果が確証バイアスです。昔の成功にとらわれて新しいやり方を頭ごなしに否定してしまう上司にならないためにも、人の話を聞かない、頑固すぎると言われないためにも確証バイアスの存在を認識して多様な意見を取り入れるように意識してみてくださいね。
現状維持バイアス
言葉の通り、変化を避けて現状維持を選択してしまうことです。デフォルト効果と相まって初期設定、当初のルールを変更したくないとバイアスが強化されてしまうことも。心身ともに疲弊しているのにリスクばかりに目が行って転職ができない、サブスクリプションやクレジットカードの年会費などの有料サービスをほとんど使用していないのに解約できないなど、非合理な行動をとってしまうのは現状維持バイアスがかかっているのが大きな要因の1つです。
確率加重関数
プロスペクト理論という有名な行動経済学の理論があり、その中の1要素です。
実際の確率と、主観で感じる確率には差があります。特に0%に限りなく近いような低い確率やほとんど100%くらいある高い確率の際に大きな歪みが生じます。
宝くじが高額当選する確率はほとんど0%です。反対に飛行機が無事に目的地まで到着する確率はほとんど100%です。それなのに宝くじはなんとなく当たりそうな気がして、飛行機はわずかに不安になったりしませんか?
ソーシャルゲームのガチャと呼ばれる制度やギャンブルが人気なのは確率加重関数によって当たるような気がするからかもしれません。もちろんご存じの通りギャンブルの結果トータルで儲けを出すことなど不可能と言っても過言ではありません。
バンドワゴン効果
人気のものが魅力的に見える心理効果がバンドワゴン効果です。
バンドワゴンとはパレードなどの先頭を進む楽隊車のことで、後に大勢の人がついてくる様からバンドワゴン効果と呼ばれています。
行列のできているラーメン屋がやけにおいしそうに見えたり、みんなが持っているブランドのアイテムが魅力的に見えることはありませんか?
ビジネスの場面ではバンドワゴン効果を利用したSNSマーケティングや口コミでの売り上げアップにつなげることができるかもしれません。
まとめ
行動経済学とは、従来の経済学に心理学の要素を含ませた学問であり、実際の人間の行動を解明するのが目的です。
思考を近道するヒューリスティックと、その結果合理的ではない選択をしてしまうバイアスがあり、人は合理的ではない意思決定を嫌になるほど繰り返しています。
そこには明らかなパターンがあり、合理的ではない意思決定をしがちな場面というものが明らかになってきています。非合理な意思決定を完全になくすことは不可能ですが、減らすことはできます。
より多くの良い意思決定ができるように行動経済学の基礎をご紹介しました。
日常生活やビジネスでも必ず役に立ちますので興味が出たらぜひ勉強してみてくださいね。
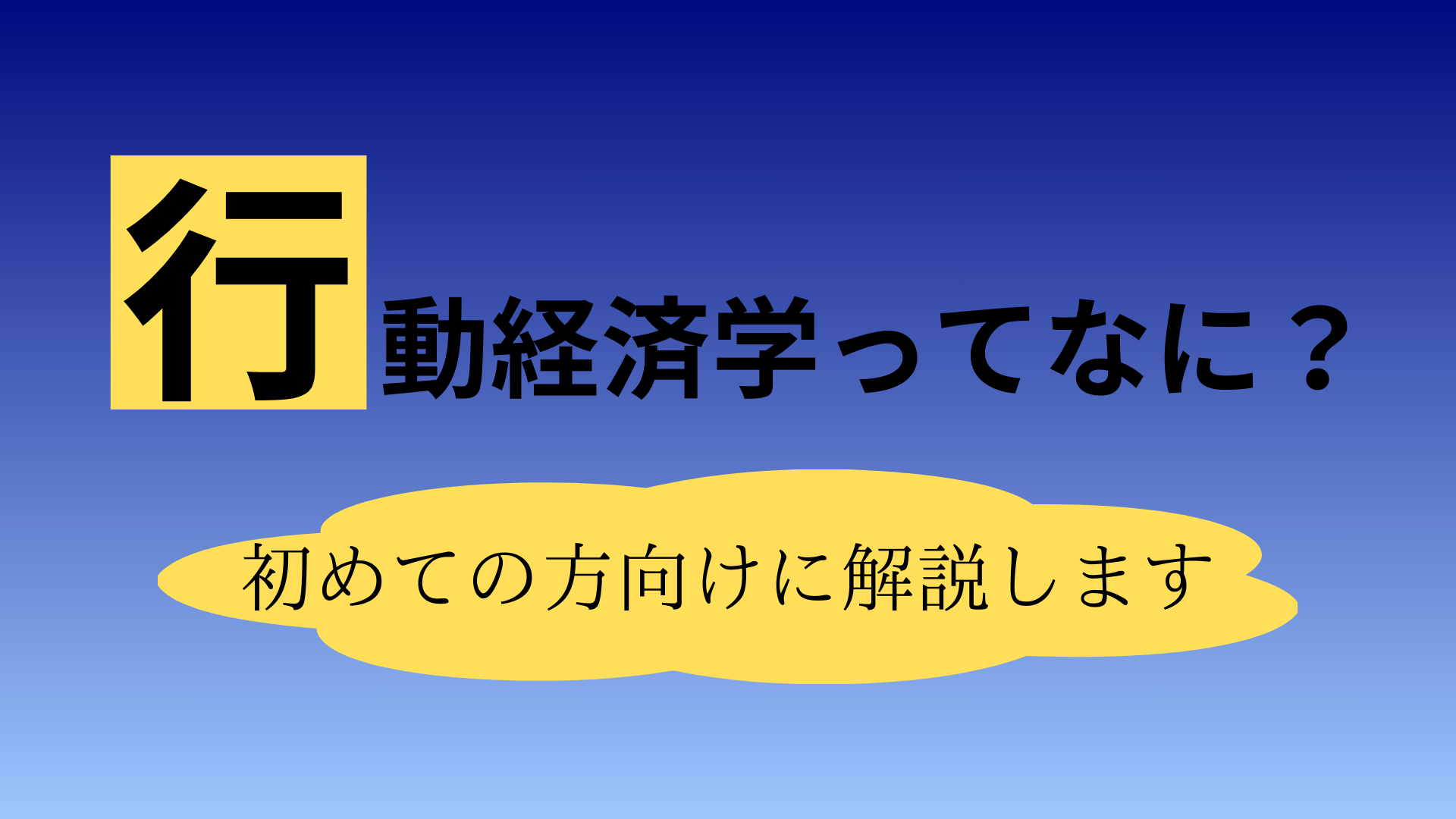





コメント