どうも、みずきちです。
ブレスト形式のミーティングをするぞ!と上司が部員を集めることがあるのですが、有意義な結果を得られた経験がありません。当たり障りのない似たような意見ばかりが出てきて、結果力を持った上司の意見が総意かのように話がまとまってしまう…。
あなたにはそんな経験はないですか?
今回はブレストに意味はあるのか、イノベーションを起こすにはどのようなブレストを実施するべきなのかを考えます。
そもそもブレストとは

ブレインストミーミング(ブレーンストーミング)の略で、日本語では集団思考、集団発想法とも言いますが、一般的にはブレストと略して呼ばれることが多いように思います。
アレックス・F・オズボーンが考案した会議方式で、参加者全員がアイデアを出し合いそれぞれのアイデアを出し合い最良の意思決定をしようというものです。
いくつかのルールや流派みたいなものがあるのですが、下記はシリコンバレーのデザイン会社IDEOの一般的なルールです。
1.結論を出さない
2.アイデアの質より量を重視する
3.ぶっ飛んだ意見を歓迎する、否定しない
4.他人の意見に乗っかる
5.テーマに集中する
よく見聞きするブレストの方法ではないでしょうか?何についてアイデアを出すのかという対象があり、その解決法を参加者で出し合ってそれを否定はしない。質を気にして発言できないなんてこともなくどんな考えであっても自由に発信ができてそれは歓迎される。
なんと素晴らしい!これで最高のアイデアが出て会社は素晴らしい方向に行くだろう!
こんなにうまくいきます?
ブレストがうまくいかない原因
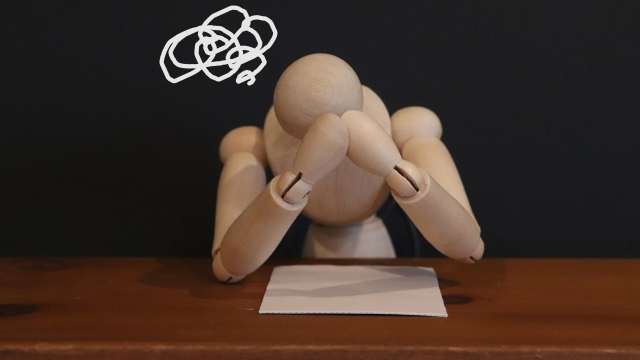
ブレストなんて意味ないよ、という言葉が多い中、ご紹介したものはなんとも素晴らしそうなものでした。それがなぜうまくいかないイメージがあるのでしょうか。上に書いたルールについて考えてみましょう。
1.結論を出さない
ブレストはあくまで意見、アイデアを創出する場であり解決法、結論を出す場ではありません。つまりブレストの結果をもとに、アイデアを統合したり取捨選択する必要があります。その後意思決定を下す会議やらなんやらで最終決定がなされるわけです。
ここで考えられる失敗は2つです。
1つはブレストで解決法が決まってしまっており、その時に出た意見に対して検討がなされないまま決定が下されてしまうことです。ブレストの特徴は質より量を意識する、でした。つまり本当に有効な施策なのか?利益をどれくらい出すことができるのか?費用はいくらかかるのか、ということを考慮していません。
その中で解決法として実行しようとすれば計画に無理が出ます。なんとか形にしようと修正を繰り返すうちに毒にも薬にもならない施策となるでしょう。なかったことにされる可能性すらあります。
もう1つは、ブレストに満足して終わってしまうことです。いくら素晴らしい意見が出ようとそれが検討実行されなければ意味がありません。「結局あの件ってどうなったの?」という社内の改革案に覚えはないですか?やってる感だけ出してしまうと当然ですが何の意味もありません。
2.3.質より量を重視し、それを否定しない
これはお互いを補足しているのでまとめます。自信がないから話せない、と素晴らしいアイデアが埋もれてしまうことを避けるために質は問わずそれを否定することも許されません。
それで全員が自主的に発言するでしょうか?そんなことはないでしょう。内容以前にこのような場で発言することが苦手な人もいるでしょうし、そんな人に無理やり意見を求めても当たり障りのない答えしか出てきません。
少数のプロジェクトメンバーのみで実施するならまだしも営業部全員とか、マーケティング部全員とか人数が多くなるほど特定の人ばかりアイデアを出すことになりかねません。
4.他人の意見に乗っかる
誰かが出したアイデアに同意できるのであれば賛同し、さらに発展させたアイデアに昇華をしていくことが目的です。メンバー同士で意見を出し合い、1のアイデアを2に、2のアイデアを10になるでしょう。
さて、ここで気になるのは質より量を重視する点です。出てくる意見には商品をピカピカに光らせようとか、反対に黒一色で高級感を出そうとか、全く統一性のない意見が多数出てきます。どれに乗っかるのが良いのでしょうか?どれに心の底から賛同できるのでしょうか?
結局誰の意見なのかが重視されます。
5.テーマに集中する
当たり前のように聞こえますよね。仮に「安いけれど品質の高い革財布を作るには?」というテーマでブレストしているときに、「そもそも今どきはキャッシュレスなんだからカードケースを作るべきでは?」とか、「スマホでなんでもできるんだからスマホカバーでしょ」とか言い出したら意見がまとまるはずがありません。
でも、このルールがイノベーションの最も大きな障壁になっているのかもしれません。
テーマに集中するとどうしても業界内の話に留まりがちです。同業他社はこうしているとか、ライバル企業の商品についている機能をウチでも採用しようとか、大きなイノベーションは起こりませんよね。
自動車メーカーのフォードはベルトコンベアを用いた流れ作業で自動車の大量生産に成功し、これまで車に手が届かなかった庶民が買えるほどコストダウンに成功しました。あなたも聞いたことがあるかもしれません。これは現代でも代表的なイノベーションとして語られます。
突然関係がない話をしてしまいましたが、お伝えしたいのはベルトコンベアのアイデアをどこで思いついたかです。この素晴らしいアイデアは会議室ではなく、食肉加工場でひらめいたのです。
一見関係がなさそうなところで、自社が抱えている課題を解決している企業が存在するというのはよくある話です。このアイデアはブレストでは出てきません。
イノベーションを起こすブレスト
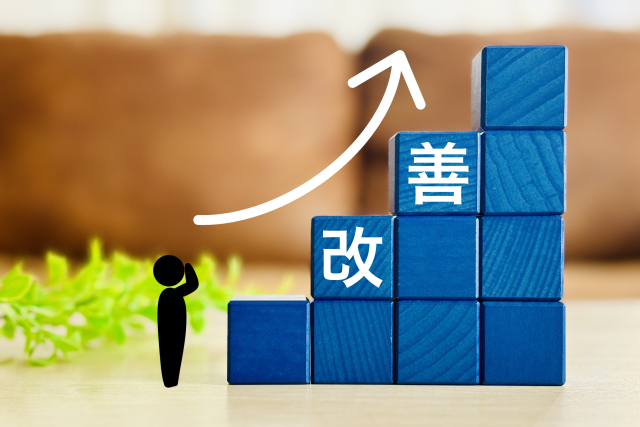
これまでひたすらブレストを否定してきました。ではブレストは意味がないのでしょうか?と聞かれるとそんなことはありません。ただし、僕が考えるブレストはほとんど1人で実施することになります。
各々がアイデアを考える
アイデアはできる限り1人で考えましょう。脳内で1人でブレストを実施し、ノートに書き写してください。
1987年、ミヒャエル・ディールとウォルフガング・シュトレーベという2人の社会心理学者がこんな実験をしました。4人1組でブレストをしたグループと、1人ずつアイデアを持ち寄った4人のグループに分けたところ、それぞれが単独で取り組んだグループのほうが生み出したアイデアは圧倒的に多かったのです。
これはどうしてなのでしょう?多面的に見た方が様々なアイデアが出てきそうなものです。しかし結果は真逆です。これまでつらつらと説明してきたことがまさに起きたのかもしれません。
ブレストとは、言ってしまえばそれぞれの経験からくるアイデアを出し合うことで、乱暴な言い方をすると「既に持っている情報の洗い出しと共有」にすぎません。小さな課題解決には繋がるかもしれませんが大きな判断には向きません。
それぞれがじっくりと考えて持ち寄ったアイデアを共有し、それについて意見を出し合うといったブレスト(もはやブレストと呼んでいいのか分かりませんが)を実施するのが効果的ではないでしょうか?
課題をしっかりと定義し、それを解決できる方法を1人でじっくりと、様々な視点から考える。
それを共有し、ああでもないこうでもないと意見を出し合う。その結果をさらに分析検討をして最終的な意思決定をおこなう。こんな方法を試してみてください。
最後に
ブレストをするとある程度の人は発言をするし、蔓延している結果を共有するだけの定例会議とは違った流れで会議が進みます。ブレストは楽しいのです。結果がどうかは別として、アイデアを生み出すという作業はなんとなく創造的な気がするし、先進的な気持ちを錯覚できます。
そう、ブレストはやってる感がとてつもなく大きいのです。ブレストをすることが目的となり、課題解決に繋がらないとか、そもそも課題を明確に定義できていないとか本末転倒ですよね。あなたがブレストに参加される際はテーマを事前に確認し、まずは1人でアイデアをひねり出してくれることを期待しています。
参考にした書籍
ジャムの法則で有名なシーナ・アイエンガー氏の書籍です。
今回書いたもの以外にも、本当に有効なイノベーションを起こす思考法について解説されています。
本当に参考になるのでぜひ読んでみてくださいね。




コメント