どうも、みずきちです。
あなたは「行動経済学」という学問を学ぼうとしてるかと思います。
最近は書籍もよく見かけるようになり、人の心を操ってビジネスをいとも簡単に成功させる、特に営業活動において行動経済学のテクニックを活用することでいとも簡単にモノが売れる!などという夢のような学問だと伝える書籍も少なくありません。
行動経済学=ビジネスに使える魔法ではありません。
書籍の選択を誤ると、間違った情報が書いているとまでは言いませんが行動経済学の本質を学ぶことができません。
今回は理解度に分けておすすめの書籍を紹介します。
行動経済学については下記の記事で詳しく紹介しています。
行動経済学とはなんぞや?という方への入門書

初めて読む書籍は、とにかくわかりやすい書籍にすることをおすすめします。
プロスペクト理論とか利用可能性ヒューリスティックとか、バンドワゴン効果とか行動経済学にはとにかくややこしい名前の心理効果が大量に出てきます。
入門用の書籍ではそれぞれの心理効果を深く学ぶことはできませんし、本質まで理解をすることは難しいかもしれません。けれど行動経済学とはどのような学問なのかを理解することができます。
ざっくり言うとどんな学問なのか、人の心理効果にはどのようなものがあるのかがなんとなくわかるようになるでしょう。
今さら聞けない行動経済学の超基本
タイトルでは超基本とされていますが、意外なほど幅広く学ぶことができます。
広く浅くではありますが、重要な心理効果は一通り紹介されています。
イラストもかなり多く、なんとなく勉強してみたいなど初めて行動経済学に触れるときはこの本をおすすめします。
たまに読み返すと勉強になるので、中級者以上の方にも読む価値がある1冊です。
行動経済学が最強の学問である
この本にも書かれていますが、行動経済学の書籍は色々な心理効果をただ羅列しているものが多く、それぞれを独立して暗記するようなものが多いです。触りとして学ぶにはいいのですが、詳しく知るにはやや物足りなかったりわかりにくい部分が目立ちます。
この本では「認知のクセ」「状況」「感情」の3つに分けて体系化されており、ビジネス向けに整理されています。なぜ人は合理的ではない意思決定するのかをわかりやすく、深く知りたいときはこの本を読んでください。
ある程度学んだあなたにおすすめの書籍

主要な心理効果や意思決定の歪みのメカニズムを理解されたら、より専門的な書籍を読んでみましょう。国や地域ごとの意思決定の差や、それぞれの主要心理効果に特化したもの、よりよい意思決定を促すための理論のようにより実践的に深く学ぶことができます。
ファスト&スロー
行動経済学を学ぶ上で、絶対に読まなければならない書籍を1冊選ぶとすると迷うことなくこれを選びます。
著者のダニエル・カーネマンは心理学者ながら、同じく心理学者であるエイモス・トベルスキーとともにノーベル経済学賞を受賞した行動経済学の創始者とも呼ばれる人物です。
人は利得よりも損失を回避するというプロスペクト理論はあまりにも有名ですのでご存じかもしれません。
この本で述べられているシステム1、システム2という概念は行動経済学に置いて非常に重要な役割を果たしています。自動的に素早い意思決定を下すシステム1と、時間をかけて努力を要するシステム2はあらゆる行動経済学の考え方に通ずるものがありますのでまさに必読書と言えるかもしれません。
NUDGE 実践 行動経済学 完全版
この本を著したリチャード・セイラーは2017年にノーベル経済学賞を受賞した経済学者です。
ナッジとは「肘で軽くつつく」といった意味を持ち、人がより良い意思決定、行動をするようにさりげなく促す施策のことで、政策や企業の戦略で利用されることが多いです。
じゃあ個人には関係ないのかといえばそんなことはありません。
企業が提供している保険の正しい選び方、より良い習慣を続ける方法や逆に悪い意思決定を促してくる企業に抵抗する手段が身につきます。
企業や機関による悪い意思決定を促す施策のことをスラッジといいます。やたらと解約をしづらくしているサブスクなどの会員サービスは代表例です。デフォルト効果を中心として、意思決定がいかにコントロールされているのかはぜひ学んでくださいね。
予想どおりに不合理
不合理であることは予想通りである、ということでなぜ人は合理的とは言えない意思決定、判断を繰り返してしまうのかを学ぶことができます。事実、データばかりでなく著者のダン・アリエリー自身が経験してきた実例を交えられているのでイメージしやすいのがこの本の特徴です。
飲食店でトッピングが無料であることに釣られて結局いつも以上にお金を使っていたり、10,000円なのか9,800円なのかで印象が変わってしまうことはないですか?タウリン1g配合より、タウリン1000mg配合のほうがたくさん入っている気がしませんか?
長い間使っていないかつ今後も使う機会は多分ないのに、いつか必要になるかも…と捨てられない物が家にありませんか?
これらは行動経済学で説明ができ、この本を読めばなぜ?がわかります。
行動経済学の使い方
研究と応用が進み、行動経済学は使う段階にきているということで、大竹文雄著の「行動経済学の使い方」を読んでみてください。
新書サイズでページ数も多くないのですが、ナッジに大きく関わるバイアスやヒューリスティックについて学べるうえ、それをビジネスやプライベートで活用する方法が書かれています。上述したナッジの考え方やまさしく使い方を知ることができるでしょう。
・目標と現実とのギャップで悩んでいる
・仕事やダイエットなどのモチベーションを保ちたい
などの悩みのヒントや公共政策についても詳しい記載があります。
NOISE
行動経済学の書籍は、バイアスをメインに据えているものがほとんどです。偏りや偏見、思い込みといった意味があり、ある程度一定方向に偏るのが特徴です。
コインが3枚連続で裏の場合、だいたいの人が次こそ表が来ると思いがちだったり、1,000円と980円では20円以上の利得を感じる人が多かったりします。
これらはまさにバイアスによるものであり、多くの人が一定方向に偏るからマーケティングにも活用されているのです。
ただし、バイアスと同じくらい気をつける必要があるのが、本書で解説されているノイズです。人によって判断が全く異なったり機嫌や時間帯に意思決定が左右されることのように、傾向がないランダムなバラつきをノイズといいます。
典型的なのは人事評価でしょうか。評価者によって重視するポイントが異なる、全体的に甘めに評価する人と厳しい人、主観で好き嫌いを評価に含めてしまうなど、誰が評価するかによってあなたの給与は大きく変わってしまうかもしれないのです。
ところがノイズはバイアスほど重視されていないのが現実です。組織はどのように判断をするべきなのか、個人としてはどのように動くべきなのかを学ぶことができるおすすめの1冊です。
最後に

本記事で紹介した書籍は、すべて読んでいます。そのうえで本当に勉強になると感じたものだけを紹介しました。
はっきり言ってしまうと、行動経済学の書籍は外れが多いです。他にもいくつも読みましたが、上記ほど学べた書籍はまずありませんでした。もちろんまだ出会っていない本がほとんどですが。
行動経済学=魔法のテクニックみたいな書き方をした書籍に騙されず正しい知識を身に着けてほしいと思います。
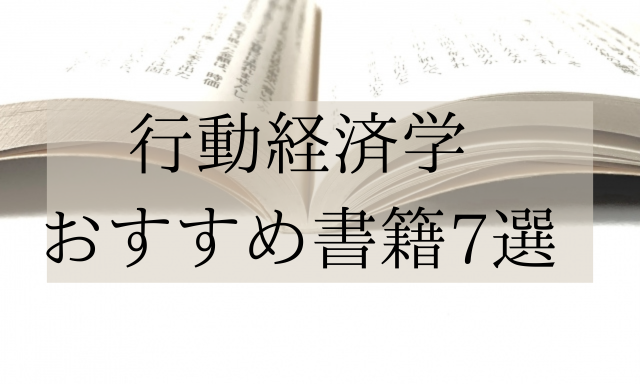





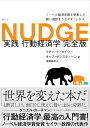






コメント